碑の詩のヘッダー
碑の詩2
長野県② 佐久市5・立科町2・南牧村2・川上村3
長野県① 長野県③ ←クリック
長野県佐久市岩村田 佐久酒造協会 |
||
昭和38年(1958)10月15日除幕<23> |
||
▼第4歌集『路上』ーー九月初めより十一月半ばまで信濃国浅間山の麓に遊べり、歌九十六首ーー ーー私は独りして飲むことを愛する。/かの宴会などといふ場合は多くたゞ酒は利用せられてゐるのみで、酒そのものを味はひ楽しむといふことは出来難い。 白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけれ 酒飲めば心なごみてなみだのみかなしく頬を流るるは何ぞ かんがへて飲みはじめたる一合の二合の酒の夏のゆふぐれ われとわが悩める魂の黒髪を撫づるとごとく酒は飲むなり 酒飲めば涙ながるるならはしのそれも独りの時にかぎれり 「酒の讃と苦笑」ーー  明治43年(1910)9月~11月の小諸滞在中の歌であるが、佐久地方は信州の酒どころ、この名歌も佐久の酒だったろうと言われ、それを聞いた酒造協会が新装なった会館の庭に歌碑を建立したのだという。「白珠の」という表記はこの地方に書き残された揮毫による。会館前庭に酒の神松尾神社の分社と並んで建っている。 なお、『牧水歌碑めぐり』によると、この歌碑と全く同じ書体の小さな歌碑が田村病院にも設置されていたという。『若山牧水 さびし かなし』にも大悟法氏が丸子町の石屋で偶然見つけ、田村病院を紹介したとあり、細かいところで異同はあるが、黒御影石の歌碑は病院の庭、洋館からは築山の陰に据えられた。著者の姉の記憶では代金9万円だったという。 |
||
| |
長野県佐久市岩村田 仙禄湖公園 |
||
建立日不明 |
||
▼第13歌集『くろ土』大正七年ーー或る頃 こころからにや少しすごせばただちに身にこたふる様なり、悲しくてーー(7首) 酒なしに喰ふべくもあらぬものとのみおもへりし鯛を飯のさいに喰ふ おろか者にたのしみ乏しとぼしかるそれのひとつを取り落したれ 人の世にたのしみ多し然れども酒なしにしてなにのたのしみ 佐久インター西側の仙禄湖というのはもともと灌漑用の人造湖で、昭和20年(1945)に疎開してきた佐藤春夫が「仙祿ハ淺間の麓、淺麓ノ字音ヲ移シ仙祿トノ文字ヲ假リ名ヅケタモノ」(佐藤春夫先生詩碑之由来)という。平成7年(1995)に整備され、有島生馬・阿部知二合同碑など文学碑をめぐる散策路が設けられている。この碑は、上段に春夫、中段は五島茂・美代子夫妻、そして下段が牧水の歌となっている。  「或る頃」一連は、病気のため禁酒していた大正7年(1918)11月初め頃の作。 ・このまま酒を断たずば近くいのちにも係るべしといふ、萎縮腎といふに罹りたればなり(4首) 飲み飲みてひろげつくせしわがもののゆばりぶくろを思へばかなしき 酒やめてかはりになにかたのしめといふ医者がつらに鼻あぐらかけり ・やめむとてさてやめらるべきものにもあらず、飲みつやめつ苦しき日頃を過す(4首) 酒やめむそれはともあれながき日のゆふぐれごろにならば何とせむ 朝酒はやめむ昼ざけせんもなしゆふがたばかり少し飲ましめ ・つとめて慎めばおのづと手持無沙汰にて喰ひたくもなき飯をばすごす(3首) 飲みすぎは酔ひてくだまくよしゑやしこのくひすぎは屁をたれてねむる ・こころからにや少しすごせばただちに身にこたふる様なり、悲しくて(7首) ・心淋しければそぞろに友が事のみ思ひ出でらる、山蘭が許に送れる戯歌数首(4首) 谷邦夫『評伝若山牧水』によれば、歌集に酒の歌が約360ほど、祖母・父母・叔父等みな酒豪で、若い時分「一升酒」の異名をとったという牧水の母は、九州での揮毫行脚の途次「酒を廃めたい」と伺いを立てた牧水に「お前の身体は酒で焼き固めてあるから廃めては不可んぞ」と言ったという。まさに酒の申し子と言うべきか。 生来の酒好きに拍車をかけたのは小枝子との苦恋。明治44年頃には電車道に酔い潰れ「電留朝臣(でんとめあそん)」とあだ名されたエピソードもある乱酔時代があった。さらには、揮毫行脚も酒びたりの生活を加速させる。「朝三四合、昼四五合、夜一升以上」の酒を51日間ほぼ毎日飲んだというのは大正14年の九州旅行だが、確実に命を縮めることとなる。 |
||
| |
長野県佐久市伴野 岸野小学校 |
||
昭和37年(1962)6月30日建立<34> |
||
******************************************* 北い 三六度一四分三二秒 東経一三八度二五分三三秒 海ばつ 六四二メートル 築池記念 昭和三七年度卒業生一同建之 ******************************************* ▼第15歌集『黒松』大正十二年ーーやよ少年たちよーー(9首) 若竹の伸びゆくごとく子ども等よ真直ぐにのばせ身をたましひを をさな日の澄めるこころを末かけて濁すとはすな子供等よやよ すみやかに過ぎゆくものをやよ子等よ汝が幼な日をおろそかにすな 子供等は子供らしかれ猿真似の物真似をして大人ぶるなかれ 老いゆきてかへらぬものを父母の老いゆくすがた見守れや子等    |
||
昭和43年(1968)10月建立 |
||
大正十四年四月若山牧水先生岸野小学校に来りわか竹の歌を揮毫さる 爾来本校教育の指針たり 昭和三年文集わか竹第一号を発刊既に十六号を数う 昭和三十八年職員この歌に曲をつけ行事式典等に歌わる 昭和四十二年秋全校児童蝗四百キロをとり歌碑の建設を計画本年十月完成をみる 昭和四十三年十月 佐久市立岸野小学校長 荻原正雄書 ************************************************************** 115名の生徒と3名の教師が卒業記念として中庭に瓢箪池を造っている途中、記念の碑も建てようということで上の歌碑が建立された。資金は生徒達が作った米やイナゴ・蕗などを売って作ったという。 しかし、縦70センチほどと小さいため新しい歌碑を作ることになり、全校生徒の協力で2メートルあまりの下の歌碑も改めて建てられた。 大正14年(1925)4月18日上野を出立して佐久地方で揮毫行脚していた牧水は、22日、社友の重田行歌が勤務していた岸野小学校で揮毫の展覧会と講演会を開いた。「聴衆は其処を始めとし付近の小学校の先生たちで凡そ七十名、僅時日の間によく手の回つたものであつた。」(『信濃の春』)その折生徒達のために書き残した半折を刻んだもので、岸野小学校では、この歌を校歌とし、学校教育目標ともしているとのこと。 歌は子ども達一般のみならず、旅人(大正2年生)・岬子(大正4年生)・真木子(大正7年生)・富士人(大正10年生)という我が子への思いを重ねて詠んだもの。 |
||
| |
長野県佐久市茂田井 武重本家酒造 |
||
昭和42年(1962)8月18日除幕<50> |
||
▼『若山牧水全歌集』補遺ーー大正十四年「御園竹讃歌」 ▼第4歌集『路上』ー九月初めより十一月半ばまで信濃国浅間山の麓に遊べり、歌九十六首ー ▼第13歌集『くろ土』大正七年ーー或る頃 こころからにや少しすごせばただちに身にこたふる様なり、悲しくてー(7首) 大正14年(1925)4月牧水が佐久地方を揮毫行脚した際に、吟醸する「御園竹」の讃歌及び二首を揮毫してもらったものをそれぞれ黒御影石に刻んで自然石にはめ込んだ歌碑。 佐久酒造協会の歌碑建設の中心となったのは武重本家酒造の武重氏であると『牧水歌碑めぐり』にあるが、仙禄湖畔の「佐藤春夫先生詩碑之由来」には、碑石の「搬出等ニツイテハオモニ望月町武重孝一氏ノ御盡力ニヨルモノデス」とあって、この地方の文化的な後見人といった存在のようである。 その武重本家酒造は、武重家十二代目が明治元年(1868)に創業。建造物三十棟が国の登録文化財で「当社のお酒は文化財の中で造られています」とホームページに謳う。「御園竹」の他に「牧水」「酔牧水」などという酒もあるようだ。    |
||
| |
長野県立科町 笠取峠 |
||
平成5年(1993)5月 |
||
▼第8歌集『砂丘』ーー山の雲ーー下野より信濃へ越え蓼科山麓の春日温泉に遊ぶ、歌四十五首ーー わがこころ青みゆくかも夕山の木の間ひぐらし声断たなくに 岨路のきはまりぬれば赤ら松峰越しの風にうちなびきつつ 老松の風にまぎれず啼く鷹の声かなしけれ風白き峰に 雲がくれひひろと啼きて行きし鳥峡間の空は光りたるかな 大正4年(1915)7月18日、転地先の北下浦から栃木県喜連川に社友の高塩背山を訪ね、さらに佐久の重田行歌の案内で、24日春日の湯へと回る。「春日の湯」という文章に「蓼科山の麓で、極く静かで、頭によく利く、是非一度来ては如何か」と前年の秋から再三勧められてはいたが、病気の妻を残して行くわけにもいかず悩んでいたところ「あとはもう大概心配ないからゆつくり行つていらつしゃい、(略)と言つて呉れるやうになつた。それならば、と喜び勇んで飛び出した」旅だったとある。そして、そこに20日あまり滞在している。 一連45首中に「山深く鳥多し」と詞書きして、燕・尾長・杜鵑各2首、鶺鴒(いしたたき)6首、鷹5首、その他3首の鳥の歌が並ぶ。「春日の湯」にも、「実に鳥が多い。彼等の啼くは朝に多く、落葉松林を離れた霧がうす雲となつて中空に棚引く頃、沢は全く此等の鳥の声に埋れてゐる。」とある。 長野県天然記念物「笠取峠の松並木」は、中山道の芦田宿と長窪宿の間にあり、小諸藩が幕府から下付された赤松を峠道約1.6キロに植樹、保護管理してきた名所で、歌川広重「木曽街道六十九次・芦田宿」に描かれているとの説明板あり。    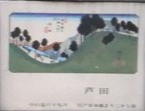 |
||
| |
長野県立科町 蓼科牧場 |
||
昭和33年(1958)6月1日除幕<22> |
||
▼第4歌集『路上』ーー九月初めより十一月半ばまで信濃国浅間山の麓に遊べり、歌九十六首ーー さらばいざさきへいそがむ旅人は裾野の秋の草枯れてきぬ 雲去れば雲のあとよりうすうすと煙たちのぼる浅間わが越ゆ 見よ旅人秋のすゑなる山山のいただき白く雪つもり来ぬ 虫けらの這ふよりもなほさびしけれ旅は三月をこえなむとする 終りなき旅と告げなばわがむねのさびしさなにと泣き濡るるらむ はつとしてわれに返れば満目の冬草山をわが歩み居り 牧水は大正14年(1925)4月、佐久地方での揮毫頒布会の折に高原の一端までは来たが、牧場まで足を踏み入れることはなかった。歌は明治43年(1910)の小諸滞在中の作。  蓼科高原に牧水歌碑を建てたいという話は早くからあったが、昭和32年秋、「白樺湖蓼科牧場の歌会に喜志子夫人が出席して蓼科山の歌を作ったことから、牧水夫妻の歌碑」(『牧水歌碑めぐり』)建立をと話が纏まり、牧場内の寄り添っているような自然石にそのまま刻んだという。左が牧水、右に 蓼科高原に牧水歌碑を建てたいという話は早くからあったが、昭和32年秋、「白樺湖蓼科牧場の歌会に喜志子夫人が出席して蓼科山の歌を作ったことから、牧水夫妻の歌碑」(『牧水歌碑めぐり』)建立をと話が纏まり、牧場内の寄り添っているような自然石にそのまま刻んだという。左が牧水、右にふくらかの立科山のたち姿佐久の花野にすそ引きのべて 喜志子   |
||
| |
長野県南牧村大字野辺山 銀河公園 |
||
平成6年(1994)5月 |
||
▼第15歌集『黒松』大正十二年ーー野辺山が原 八が嶽北側の裾野を野辺山が原といふ、念場が原より更に広く更に高き高原なりーー(16首) 野末なる山に雪見ゆ冬枯の荒野を越ゆとうち出でて来れば 大空の深きもなかに聳えたる峰のたかきに雪降りにけり 甲斐が嶺のむら山のなかのひとつ山峰のたかきに雪降りにけり 人いまだゆかぬ枯野の今朝の霜を踏みてわがゆくひたに真直ぐに わが行くや見る限りなる霜の野の薄枯れ伏し真しろき野辺を はりはりとわが踏み裂くやうちわたす枯野がなかの路の氷を 枯れて立つ野辺のすすきに結べるは氷にまがふあららけき霜 わが袖の触れつつ落つる路ばたの薄の霜は音立てにけり 八が嶽峰のとがりの八つに裂けてあらはに立てる八が嶽の山 昨日見つけふもひねもす見つつゆかむ枯野がはての八が嶽の山 山梨県小淵沢・高根に続く「木枯紀行」の旅である。 この旅は、撰文にある通り大正12年(1923)10月28日沼津を発って河口湖・精進湖畔を巡り、小淵沢から念場ヶ原・野辺山ヶ原を抜けて松原湖畔に門人等と落ち合う。いったん佐久まで出たあと再び野辺山ヶ原の市場村に宿り(8日)、9日千曲川上流を歩いて梓山村泊、10日十文字峠を越えて秩父に出、12日東京に一泊して帰宅したのであった。 この旅の歌は『黒松』に91首収められている。 ・念場が原ー八が嶽の裾野を甲斐より信濃へ越えむとして念場が原といへるを過ぐ、方八里に及ぶ高原なり(10首) ・松原湖畔雑詠ー信濃南佐久郡なる松原湖畔の宿屋に同国の友人数名と落合ひ数日を遊び暮しぬ(19首)一夜ふとしたる事より笑ひ始めて 一座五人ほとほと脊骨の痛むまでに笑ひころげぬ(8首) ・佐久風物ー松原湖畔を出でてよりなほ数日、南北佐久両郡に亘る佐久高原をさまよひ歩きぬ(13首) ・野辺山が原(16首) ・千曲川上流ーその一、市場村附近(2首) その二、大深山村附近(9首) その三、梓山村附近(14首)  「東日本鉄道最高駅野辺山」「標高一三四五米六七」の標柱がある野辺山駅前の銀河公園(宇宙に一番近い駅として有名だそうだから?)に、八角柱8面に歌と撰文を刻んだ極めてユニークな歌碑。撰文には「記念とされたる八首」とあるが、実際には7面に7首、1面は撰文が占めている。また、撰文では11月8日に松原湖畔からまっすぐ来たように読めるが、「木枯紀行」によると4日には重田行歌宅を布施村に訪い、5日「総勢岩村田に出で、其処で別れる事になつた」が、大澤茂樹と馬流1泊・湯沢の湯2泊して、8日市場村に宿泊している。    |
||
| |
長野県南牧村海ノ口 馬市場跡 |
||
平成6年(1994)5月 |
||
▼第15歌集『黒松』大正十二年ーー千曲川上流ーー(25首) 見よ下にはるかに見えて流れたる千曲の川ぞ音も聞えぬ 入りゆかむ千曲の川のみなかみの峰仰ぎみればはるけかりけり (その一、市場村附近) 「十一月八日 誘ひつ誘はれつする心はとうとう二人(註:牧水と大澤茂樹)を先日わたしと中村君と昼食した市場といふ原中の一軒家まで連れて行つた。(略)二階は十六畳位ゐも敷けるがらんどうな部屋であつた。年々馬の市が此処の原に立つので、そのためのこの一軒であるらしい。」(「木枯紀行」)  明治20年(1887)に馬市場が開設され、木曽に次ぐ大きな馬市として小諸在住の藤村も見物に訪れたほどであったが、昭和30年(1955)の年度末に廃止されたという。また、この地はほぼ日本の中央に位置し「公共測量の基準点」が置かれているため「日本のおへそ」として売り出しているようだ。その「基準点」が、3月11日の東日本大地震でずれたという。    |
||
| |
長野県川上村秋山 町田市自然休暇村 |
||
平成2年(1990)4月建立 |
||
▼第15歌集『黒松』大正十二年ーー千曲川上流ーー(25首) 見よ下にはるかに見えて流れたる千曲の川ぞ音も聞えぬ 入りゆかむ千曲の川のみなかみの峰仰ぎみればはるけかりけり (その一、市場村附近) 「十一月九日 早暁、手を握つて別れる。彼は坂を降つて里の方へ、わたしは荒野の中を山の方へ、久しぶりに一人となつて踏む草鞋の下には二寸三寸高さの霜柱が音を立てつつ崩れて行つた。/また、久し振の快晴、僅か四五日のことであつたに八ヶ嶽には早やとつぷりと雪が来てゐた。野から仰ぐ遠くの空にはまだ幾つか山々が同じく白々と聳えてゐた。踏み辿る野辺山が原の冬ざれも今日のわたしには  何となく親しかつた。 何となく親しかつた。野末なる山に雪見ゆ冬枯の荒野を越ゆと打ち出でて来れば 昨日見つ今日もひねもす見つつ行かむ枯野がはての八ヶ嶽の山 見よ下にはるかに見えて流れたる千曲の川ぞ音も聞えぬ 入り行かむ千曲の川のみなかみの峰仰ぎ見ればはるけかりけり おもうて来た千曲川上流の渓谷はさほどでなかつたが、それを中に置いて見る四方寒山の眺望は意外によかつた。」(「木枯紀行」) 休暇村入口駐車場脇に建てられている。 |
||
| |
長野県川上村 大深山考古館 |
||
昭和60年(1985)11月6日 |
||
*************************************************************** 大正十二年若山牧水当地に於て詠める 牧水生誕百年を記念して 歌詞はは牧水子息旅人書 白峰会建之 *************************************************************** ▼第15歌集『黒松』大正十二年ーー千曲川上流ーー ゆきゆけどいまだ迫らぬこの谷の峡間の紅葉時すぎにけり 泥草鞋踏み入れて其処に酒をわかすこの国の囲炉裡なつかしきかな とろとろと榾火燃えつつわが寒き草鞋の泥の乾き来るなり 居酒屋の榾火のけむり出でてゆく軒端に冬の山晴れて見ゆ (その二、大深山村附近)  「とある居酒屋で梓山村に帰りがけの爺さんと一緒になり、共にこの渓谷のつめの部落梓山村に入つた。そして明日はこの爺さんに案内を頼んで十文字峠を越ゆることになつた。」(「木枯紀行」十一月九日) 縄文時代中期の遺跡大深山遺跡の出土品を収蔵・展示していた「考古館」だが、平成7年(1995)に川上村文化センターが開設され、収蔵品は全てそちらに移され建物のみが残るという。 |
||
| |
長野県川上村梓山 金峰山神社 |
||
昭和60年(1985)11月建立 |
||
*************************************************************** 大正十二年本村において詠める 漂泊の歌人若山牧水生誕百年を記念して建立する 揮毫は牧水の長子である 昭和六十年十一月 川上村 *************************************************************** ▼第15歌集『黒松』大正十二年ーー千曲川上流(その三、梓山村附近) この国の寒さを強み家のうちに馬引き入れて共に寝起す 寒しとて囲炉裡の前に厩作り馬と飲み食ひすこの里人は まうまると馬が寝てをり朝立の酒沸かし急ぐゐろりの前に まろく寝てねむれる馬を初めて見きかはゆきものよ眠れる馬は 梓山の宿屋に入ったものの、同宿となった役人連中の傍若無人さに耐えかね、「先刻知り合ひになつた爺さん」に他の木賃宿へ案内してもらう。 「木賃宿とは云つても古びた堂々たる造りで、三部屋ばかり続いた一番奥の間に通された。(略)二間ほど向うの台所の囲炉裏端でもそろそろ夕飯が始まるらしく、家族が揃つて、大賑かである。わたしはとうとう自分のお膳を持つてその焚火に明るい囲炉裏ばたまで出かけて仲間に入つた。/最初来た時から気のついてゐた事であつたが、此処では普通の厩でなく、馬を屋内の土間に飼つてゐるのであつた。津軽でもさうした事を見た。余程この村も寒さが強いのであらうと二疋並んでこちらを向いてゐる愛らしい馬の眼を眺めながら、案外に楽しい夕餉を終つた。(略)  十一月十日 満天の星である。切れる様な水で顔を洗ひ、囲炉裡にどんどんと焚いて、お茶代りの般若湯を嘗めてゐると、やがて味噌汁が出来、飯が出来た。味噌汁には驚いた。内儀は初め馬の秣桶で、大根の葉の切つたのか何かを掻きまぜてゐたが、やがてその手を囲炉裡にかかつた大鍋の漸くぬるみかけた水に突つ込んでばしやばしやと洗つた。その鍋へ直ちに味噌を入れ、大根を入れ、斯くて味噌汁が出来上つたのである。/馬たちはまだ寝てゐた。大きい身体をやや円めに曲げて眠つてゐる姿は、実に可愛いいものであつた。毛のつやもよかつた。これならお前たちと一つ鍋のものをたべても左程きたなくはないぞよと心の中で言ひかけつつ、味噌汁をおひしくいただいた。」(「木枯紀行」) ページの先頭へ |











